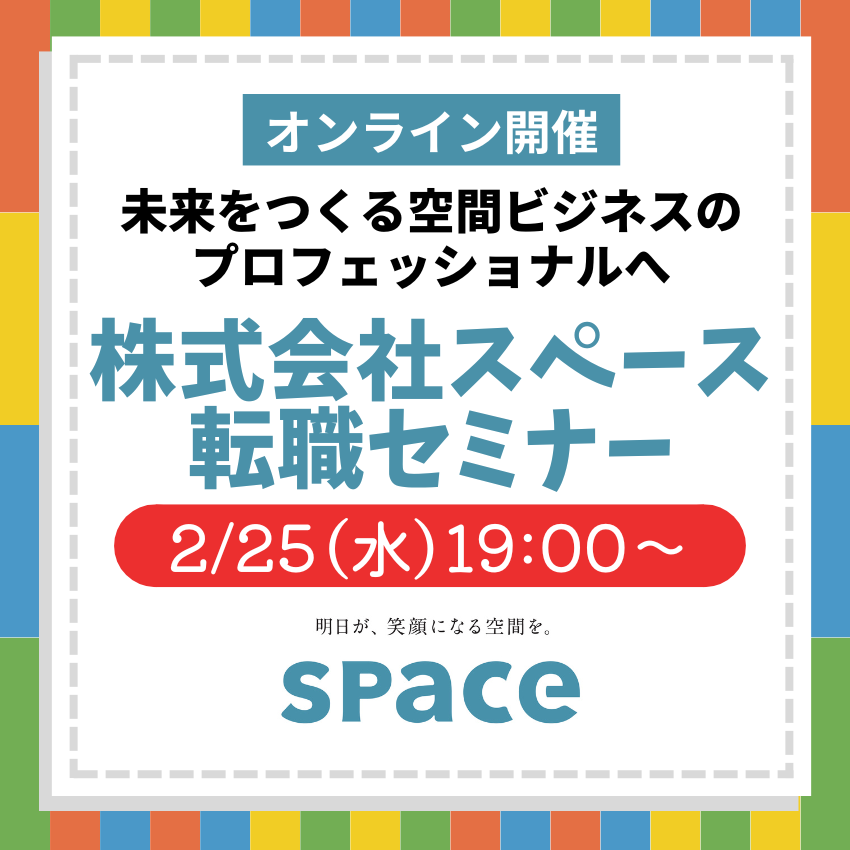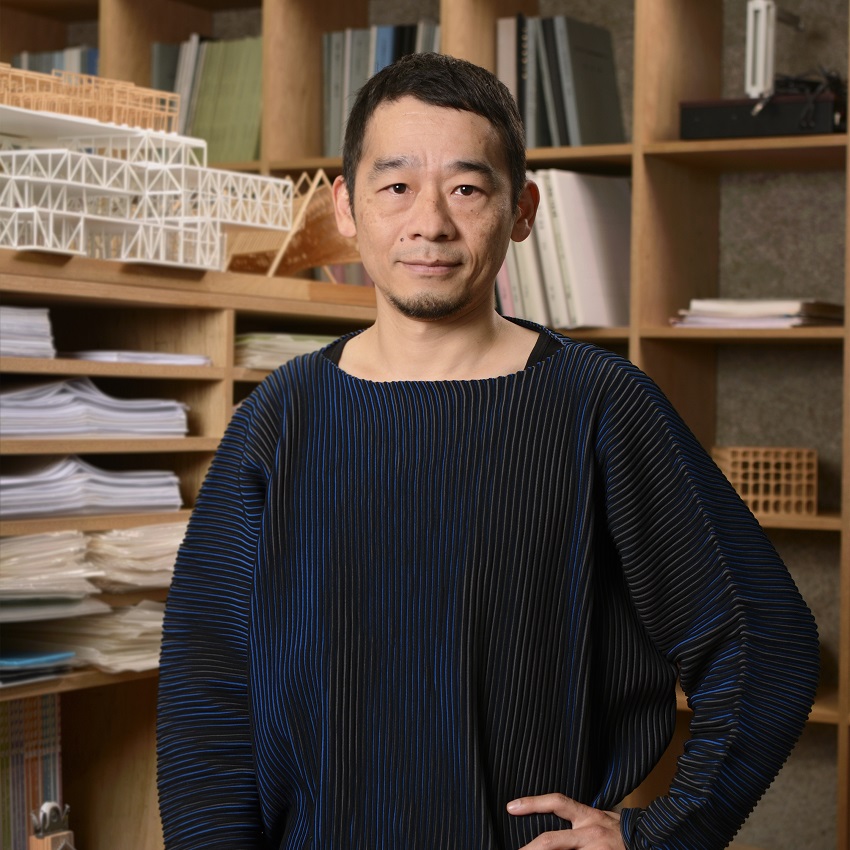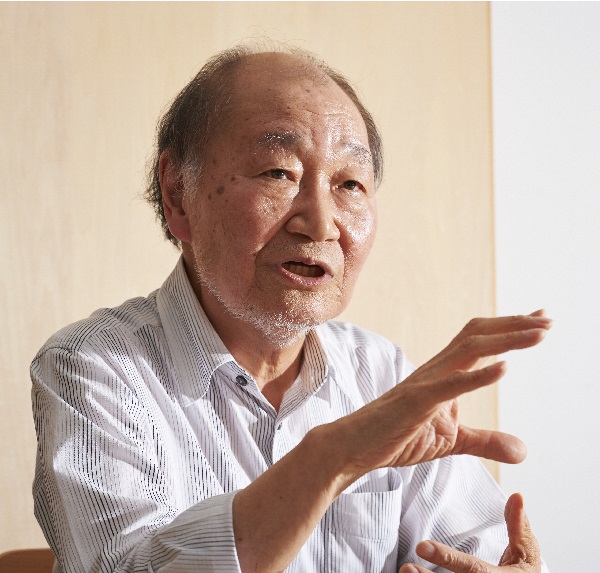広く建築や都市、そして人々と真正面から向き合っていく。未来のために職能を生かすのが僕たち建築家の役割なのだから
迫 慶一郎
「中国で最も活躍する建築家の一人」。多くのメディアは、迫慶一郎をそう称する。事実、迫がこれまで手がけたプロジェクトの8割以上は、中国での仕事が占める。それも、都市のランドマークになるような巨大プロジェクトばかりだ。現在は北京、東京、福岡の3拠点に事務所を構え、ロシアや中東などからもオファーが舞い込んでいる。44歳と、業界にあっては若手ながら、世界に羽ばたく様は華々しい。しかしその裏側には、すさまじい働きと、どのような逆境にも屈しない〝挑み〞の連続がある。「建築家の本分は社会に貢献し、未来をつくること」。そう言い切る迫は、今、建築家という枠を超えて、震災による被災地復興や、企業のブランディングも手がけるなど、マルチな活動に精力を注ぎ込む。常に全力疾走――それが、迫の生き方だ。
文武に長けた少年。建築家という職業に早くから憧れを持つ
7歳の時、航海士だった父親と早すぎる死別をした迫は、母方の実家がある福岡県春日市に移り住んだ。同地には溜池がたくさんあり、水場や自然に恵まれた環境で、迫は伸び伸びと育った。経済的に楽ではなかったが、3人の子供たちに苦労を感じさせず、何でも自由にさせてくれた母親。そのバイタリティは、迫自身が受け継いでいる。
●
働きながら、いつも忙しく動き回っていた母に負担はかけたくないなぁと思いつつも、けっこうやんちゃでした。僕は器用なほうで、スポーツも勉強もできたものだから、ちょっと生意気すぎるところがあって、学校の先生に食ってかかったりね。高校生の時には、流行っていたマージャンをやっているのを見つかって、担任にビンタ食らったり(笑)。でも母は、僕のすること、望むことをいつも信じて支えてくれた。今でも頭が上がりません。
春日市は野球が盛んな地で、僕も小学生でソフトボールをやり始め、以降、ずっと野球少年です。福岡県立筑紫丘高校の野球部では副キャプテンも務めました。僕は足が速かったし、器用だから、守備はどこでもOK。ただ小柄なので、レギュラーになるために、人一倍努力したのも確かです。
3年の夏、甲子園を目指した県大会準々決勝は、忘れられません。9回裏敗戦ムードが漂うなか、僕は先頭打者として打席に立ったのですが、息もできないほどの重圧を感じたものです。でもそれを跳ね返し、ヘッドスライディングで出塁。結果、ゲームの流れが変わって逆転勝利できた。「歯を食いしばり、本気で取り組めば不可能はない」――そう思えた瞬間でした。野球部時代に培った経験は、今も仕事をするうえで、根底に息づいています。
●
迫が「建築家になる」と決めたのは、小学校5年生の時と早かった。趣味ながら、庭の灯籠や池まで自作していた祖父の影響があるのだろう。近所で頼もしく家を建てていく大工の姿にも憧れていたそうだ。以来、職業観に変わりはなく、迫は大学進学にあたり、当然のごとく建築学科を志していた。
●
最初は、九州大学を受験したんです。しかし、現役合格ならず。野球に打ち込みながらも、成績は悪くなかったし、ずっと望みどおりの人生を送ってきたから、どこかで「自分はちょっと特別」みたいな意識があったんですよ。初めての挫折でした。ショックで何もする気になれない幽体離脱状態。それが3カ月くらい続いたでしょうか。ある時、ふと立ち寄った高校の野球グラウンドで、後輩たちが必死に練習している姿を見ていたら、滝のように涙が出てきて……。それで現実を受け入れられ、真剣に野球をやっていた感覚が戻って、一気にラクになったのです。
今思えば、挫折があってよかった。すんなり現役合格していたら、僕はとんでもない勘違い野郎になっていたかもしれない(笑)。人生って、そんな偶然の積み重ね。どこかを切り取れば、人はいつも岐路に立たされているものだと思うんですよ。
で、翌年に合格したのが東工大。母には〝事後報告〞でしたが、この時も何も言わず、上京させてくれました。入学早々、勧誘されて体験試乗したヨットがすごく面白くて、さっそく入部。海で日焼けした集団がカッコよかったし、今度は、自然を相手にするスポーツに夢中になりました。ただ始めてみると、だんだん学校に行けないことがわかってきた。合宿生活が長く、一番練習していた時は、半年間くらい海にいますから。加えてヨットはお金がかかるので、バイトも忙しい。留年しなかった学生のなかでは、僕、ダントツで学校に行っていないと思います。
選手としては大したことはなかったけれど、海が何なのかを知ったのは、僕にとって大きかった。本当に美しいと思う瞬間、そして命の危険を感じる瞬間、その両方を何度も味わいました。この時の経験がのちの仕事に生きたし、今、力を注いでいる震災復興のプロジェクト「東北スカイビレッジ」構想にも影響しています。本当に、すべてはつながっているんだと思いますね。
- 【次のページ】
- 意中の師匠に就き、トレーニングを積む。鍛えられ、開花した才

- 迫 慶一郎
1970年7月16日 福岡県福岡市生まれ
1996年3月 東京工業大学大学院
理工学研究科建築学専攻修了
1996年 4月 山本理顕設計工場入所
2004年2月 SAKO建築設計工社設立
2004年9月 米国コロンビア大学客員研究員、
文化庁派遣芸術家在外研修員
(~2005年)
- 主な受賞歴
<2013年>
蔵前ベンチャー賞
<2012年>
GOOD DESIGN IS GOOD BUSINESS
China Awards 2012(中国)
<2010年>
2009-2010年度国際設計芸術成就賞(中国)
<2009年>
Euro Shop Retail Design Award 2009
One of Three Best Stores Worldwide
<2008年>
グッドデザイン賞
現代装飾国際メディアプライズ2007(中国)
ベストデザイナー賞
ほか、JCDデザインアワード(2004年より11年連続)
など多数