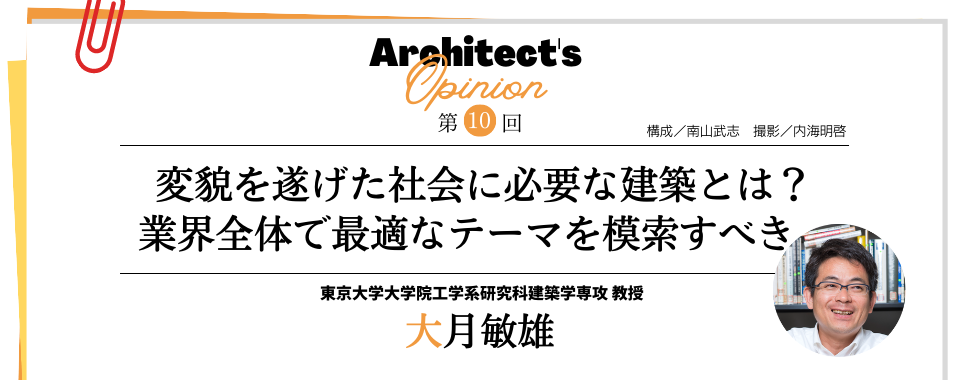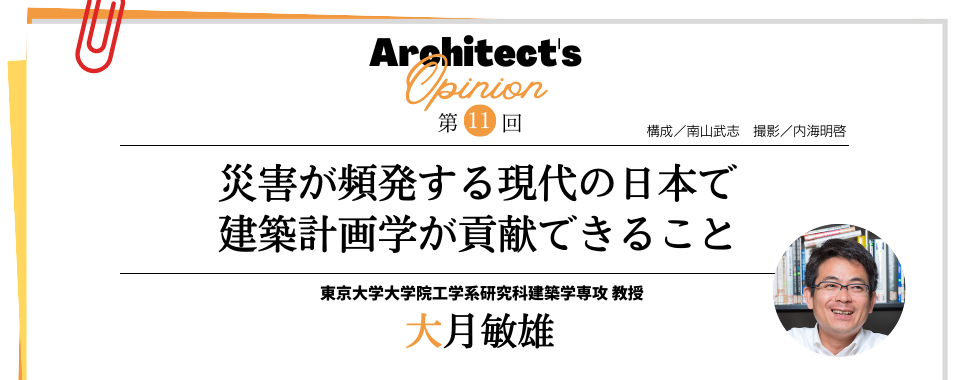これからの日本社会を考えれば、伝統の継承と新たな工夫が調和・融合する“創造的なまちづくり”は非常に重要なテーマである
三井所清典
50年を超える道のりにおいて、三井所清典は常に研究開発と実践を両軸に活動してきた。それは、設計だけにとどまらない「建築家が持つ多様な職能」を体現するものだ。大学院時代から携わった住宅の工業化、商業施設のシステムズ・ビルディングの開発では時代に先駆けた事績を残し、個々の建物に対しても、建築の目的と同時に手段について広く考察する姿勢を貫いてきた。また、1980年に竣工した「佐賀県立九州陶磁文化館」の仕事を機に始めたまちづくり活動は、三井所のライフワークとなっている。現在は日本建築士会連合会の会長として、地方独自の文化・風土を踏まえた建築設計と、それを担う「まちづくり建築士」の活動推進に心血を注ぐ。三井所が見据えているのは産業全体と、その未来である。
重ねてきた実績を生かし、より大局的な観点から創造的な活動を推進
三井所は被災地の復興支援にもかかわっており、復興住宅のモデル設計を通じて各地で重要な活動を行ってきた。その最初は、2004年に発生した新潟県中越地震。長岡市の山古志地域では、無被害の住宅0棟という甚大な被害に見舞われた。住宅の再建を目的に設置された委員会に呼ばれた三井所は「中山間地型復興住宅」を開発、ここでも地域に根ざす建築を貫いている。

●
「山古志らしい住まい」「雪と上手に付き合う住まい」「コスト負担を軽減する住まい」などといった基本方針を元に提案をまとめていきました。なかでも大切にしたのは〝小さな未完成の住宅〞にすること。大きな家をつくっていたら時間もお金もかかって、早急な住まいの再建と生活の再建に応えられません。そして未完成というのは、10年後、20年後の増改築を想定してのことです。震災後もずっと、地域の大工、工務店が生業を継続できなければ、その先で困るのは村民なのですから。社会のシステムとして重要であり、それをどう維持するかを考えながら進める、というのが提案の最大の柱でした。
委員会ではプレハブ提案の声もあったんですけど、メンテナンスが大変で都市部のようにはいきません。また外壁などは、当時はセメント系や金属系の長尺をバンバン張っていく方法が主流でしたが、それもやめませんかと。先々を考えると、同じ材料が手に入らなくて全部取り替えになってしまう。古めかしい感じはするけれど板張りにすれば大工による修理も利くし、将来的にはいいでしょう……といった具合に、現地でワークショップを重ねながら「成長させていける住まいの仕組み」を詰めていったのです。
6タイプの基本型と復興集落のイメージを提出したのは震災1年後、数多くの住宅建設を実現する供給体制を構築できた。また地域の建築士、工務店、材料メーカーとの協力関係を通じて得たノウハウは、ほかの被災地での発展的復興住宅の建設にも生きています。
●
研究開発、設計、そして教育の現場で、三井所は地域に根ざす建築的環境の創造を主眼に活動してきた。まさにライフワークである。12年に日本建築士会連合会会長に就任してからは、それらの発想や実績を生かし、より大局的な観点で活動の推進にあたる日々だ。
●
地方にはそこの文化・風土を踏まえた素晴らしい建築技術があります。ただ、それを生かす機会が少ない。独自の技術を生かしたほうが魅力的な建築になるのに、実際にはほとんど標準化してしまっているでしょう。東京への一極集中も問題です。これからの社会を考えれば、継承と工夫が調和する〝創造的なまちづくり〞はとても重要なテーマで、そこに基づいた活動を推進していくのは、連合会会長としての私の大きな役割だと考えています。
木造建築の復活、推進もその一環です。実は、新国立競技場の建設に向けて採用されたザハの案が白紙撤回された時、私たち連合会は「木造でできる」という提案を発信したんですよ。いろんな建設会社に対し、「新しく応募をされるのなら一度は木造の屋根も検討してくれませんか」って。日本中から木を集めれば全国が寄与したことになるし、エネルギーもそんなにかからないといった利点を話しながら。結果としては、木を取り入れたスタジアム建設が進んでいますから、多少なりとも動けたのかなと思っているんです。
日本的な建築って、残念ながら日本のなかで「いいね」という概念が確立されていない。明治以来続いている欧米の建築教育の下で、西洋の建築ばかりやってきましたからね。日本が世界と肩を並べていくために西欧化しようと、時代をつくってきた先人には感謝するけれど、「もういいじゃない」という時期に来ていると思うのです。考えてみれば、大学教育のなかに「日本建築学科」はないわけで、これはおかしいでしょう。美術や音楽にはあるし、文学にいたっては国別にジャンルが存在します。言葉と同じように、そして地方に方言があるように、日本には長い歴史のなかで文化として育まれた建築がある。インターナショナルなデザインの標準化をよしとする考えには、やはり危機感を覚えますね。そういう発信も含めて、これからの社会をつくるために、自分の役割を精一杯果たしていきたいと思っています。
※本文中敬称略

- 三井所清典
1939年2月7日 佐賀県神埼町(現神埼市)生まれ
1963年3月 東京大学工学部建築学科卒業
4月 RAS設計同人参加
1965年3月 東京大学大学院数物系研究科
建築学専攻修士課程修了
1968年3月 東京大学大学院工学系研究科
建築学専攻博士課程修了
4月 芝浦工業大学講師
1970年8月 アルセッド建築研究所設立
1973年4月 芝浦工業大学助教授
1982年4月 芝浦工業大学工学部建築学科教授(現名誉教授)
2007年4月 東京建築士会会長
2012年4月 日本建築士会連合会会長
家族構成=妻、息子2人
- 主な受賞
日本建築家協会優秀建築賞、
日本建築学会作品選奨、
日本建築家協会環境建築賞 最優秀賞、
BCS賞、
日本建築家協会新人賞、
新建築賞、
日本商環境設計家協会 JCDデザイン賞 大賞、
GOOD DESIGN AWARD 金賞、
ARCASIA Awards for Architecture 2016,
Building of the Year、
WAN Sustainable Buildings of the Year, Winner、
ar+d Awards, First Prize
ar+d Awards for Emerging Architectureほか多数