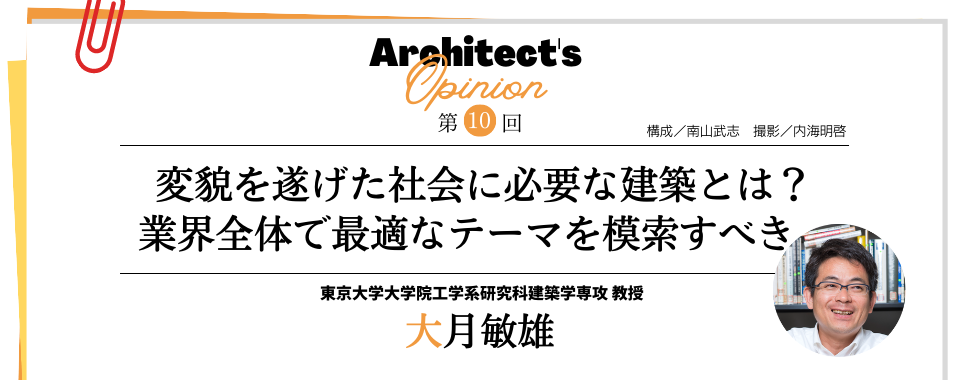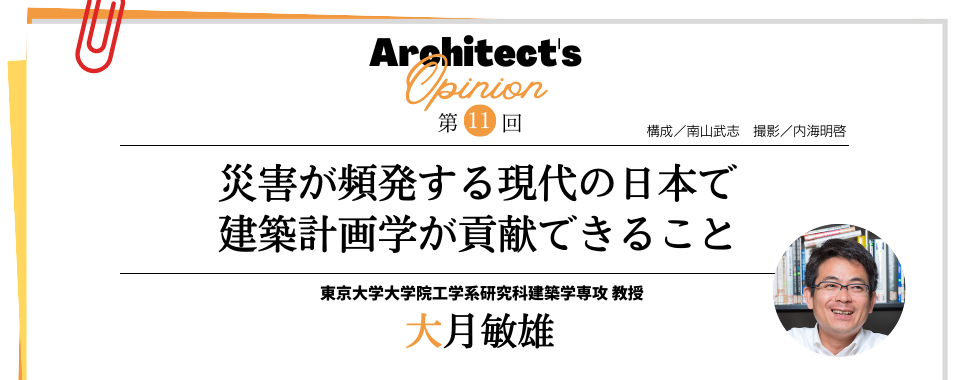これからの日本社会を考えれば、伝統の継承と新たな工夫が調和・融合する“創造的なまちづくり”は非常に重要なテーマである
三井所清典
50年を超える道のりにおいて、三井所清典は常に研究開発と実践を両軸に活動してきた。それは、設計だけにとどまらない「建築家が持つ多様な職能」を体現するものだ。大学院時代から携わった住宅の工業化、商業施設のシステムズ・ビルディングの開発では時代に先駆けた事績を残し、個々の建物に対しても、建築の目的と同時に手段について広く考察する姿勢を貫いてきた。また、1980年に竣工した「佐賀県立九州陶磁文化館」の仕事を機に始めたまちづくり活動は、三井所のライフワークとなっている。現在は日本建築士会連合会の会長として、地方独自の文化・風土を踏まえた建築設計と、それを担う「まちづくり建築士」の活動推進に心血を注ぐ。三井所が見据えているのは産業全体と、その未来である。
エンジニアになると決めていた少年時代。大学で設計に魅了される
故郷は佐賀県神崎町。通った地元の小学校には立派な木造建築の講堂があり、今も三井所の心に深く残っている。古く35年に建てられたものだが、教育施設と町民が利用する公共施設を兼ねたもので、当時の発想としては斬新だった。この時、建設運動を率いたのは町長を務めていた祖父であり、後の三井所に少なからず影響を与えている。

本取材は、2019年5月、アルセッド建築研究所(東京渋谷区)のオフィスで行われた。明治通りと青山通りのほぼ中間に位置した静かな環境であった
●
「ちょこ米運動」という名の下、各家庭が食事のたびに米を盃一杯分ずつ抜いて、それらを集めて建設資金に充てたと聞いています。もちろん公金も入っていたと思いますが、「自分たちの施設は自分たちでつくる」、まさにまちづくりの要となる姿勢ですよね。祖父はいい働きをしたのでしょう、講堂には大きな写真が飾られていました。
というわけで「おじいさんは立派だった」とよく聞かされ、小学校にはお袋が教師としていたものだから、私は少々窮屈な生活を送っていました。成績も良かったから児童会長をやり、野球部ではキャプテン、さらにスポーツや文化系の大会にも全部出なくちゃいけない。まぁ田舎ですからね、役割が集中するんですよ。解放されたのは中学、高校に進学してから。いずれも佐賀市で、汽車通学で〝都会〞に出るとすごく洗練された感じがあったし、いろんな役割を担う活発な人がたくさんいた。何もしなくてもいい立場になった私はすっかり解放され、ずっと好きだった絵をよく描いていました。
「将来何になるか」については、小学生の頃からエンジニアになると決めていたんです。これは、お袋の教育が大きかったと思う。いつだったか、私は「戦死した親父の敵を討たねば」と息巻いたことがあったのですが、お袋にこっぴどく叱られましてね。私世代が幼児教育として受けてきた軍国主義を否定し、「文化や経済で敵を討てるような力をつけなさい」って。一方で、佐賀が米所になったのは、佐賀藩の武士、成富兵庫茂安が成し遂げた治水事業があったからこそ、という地元話もあり、日本に工業力をつけていくにはエンジニアの存在が重要なんだと。そんな思いをずっと持ち続けていました。
●
「どうせ出るなら東京へ」―― 志を胸に進学したのは東京大学理科Ⅰ類。この頃の三井所は、建築家というものの存在をまだ知らなかったそうで、「現場で建築ができると思っていた(笑)」。〝設計〞という領域があることを知り、その面白さに魅せられたのは工学部、専門課程に入ってからだ。
●
世の中には設計なるものをする人がいて、図面や模型に基づいて工事が行われるという流れを初めて知ったんですよ。授業が面白く、次第に設計にはまっていきました。課題に夢中になって徹夜する日もザラ。入学時から熱心にやっていた空手部の練習もままならなくなり、3年になってからは建築一本の生活です。クラスの仲間が芸能人の別荘の注文を取ってきた時などは、皆で嬉々として設計したものです。その設計料でヨットを買って、湘南ボーイを気取ったのもいい思い出(笑)。
卒業論文は、当時助教授だった内田祥哉先生の下で取ることにしました。この頃には、将来は設計者になると決めていましたが、内田研で博士課程にいた先輩、原広司さんから「構法や性能的な視点を持って建築設計を学ぶ場」だと聞いたから。元々エンジニア志向の私には近しい感覚がありました。折しも、性能をちゃんと押さえた〝科学的な建築〞の重要性が高まっていた時代で、世の中に必要なんだという意識も強かったですね。
卒論のテーマは「公団住宅の断熱性能と遮音性能に関する基礎的研究」。公団住宅の質を上げるために性能はどうあるべきかを研究したものです。大学院には、設計や工事に関してだけでなく、例えば建物の外壁の汚れを研究する先輩もいたりして、驚くやら面白いやら。建築という分野にはまだまだ解明されていない問題があって、それらを一つひとつ解いていかないと建築は発展しない。そんな当時の思想は、私にも染み込んでいたように思います。
- 【次のページ】
- 建築工業化から地域に根ざす建築・まちづくり活動へ

- 三井所清典
1939年2月7日 佐賀県神埼町(現神埼市)生まれ
1963年3月 東京大学工学部建築学科卒業
4月 RAS設計同人参加
1965年3月 東京大学大学院数物系研究科
建築学専攻修士課程修了
1968年3月 東京大学大学院工学系研究科
建築学専攻博士課程修了
4月 芝浦工業大学講師
1970年8月 アルセッド建築研究所設立
1973年4月 芝浦工業大学助教授
1982年4月 芝浦工業大学工学部建築学科教授(現名誉教授)
2007年4月 東京建築士会会長
2012年4月 日本建築士会連合会会長
家族構成=妻、息子2人
- 主な受賞
日本建築家協会優秀建築賞、
日本建築学会作品選奨、
日本建築家協会環境建築賞 最優秀賞、
BCS賞、
日本建築家協会新人賞、
新建築賞、
日本商環境設計家協会 JCDデザイン賞 大賞、
GOOD DESIGN AWARD 金賞、
ARCASIA Awards for Architecture 2016,
Building of the Year、
WAN Sustainable Buildings of the Year, Winner、
ar+d Awards, First Prize
ar+d Awards for Emerging Architectureほか多数