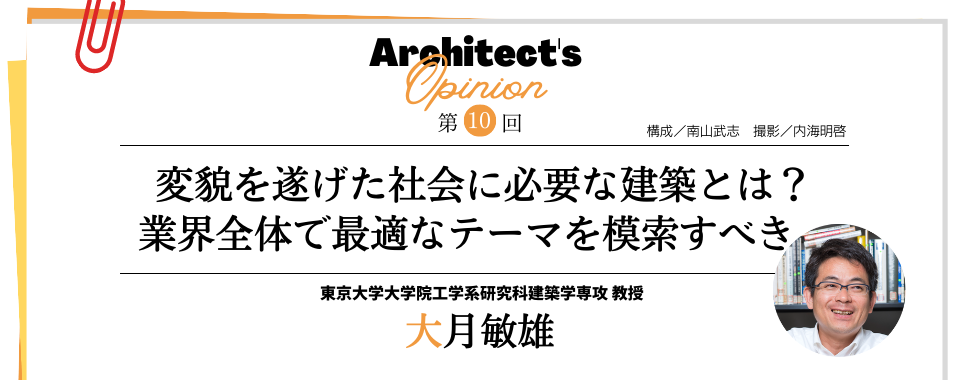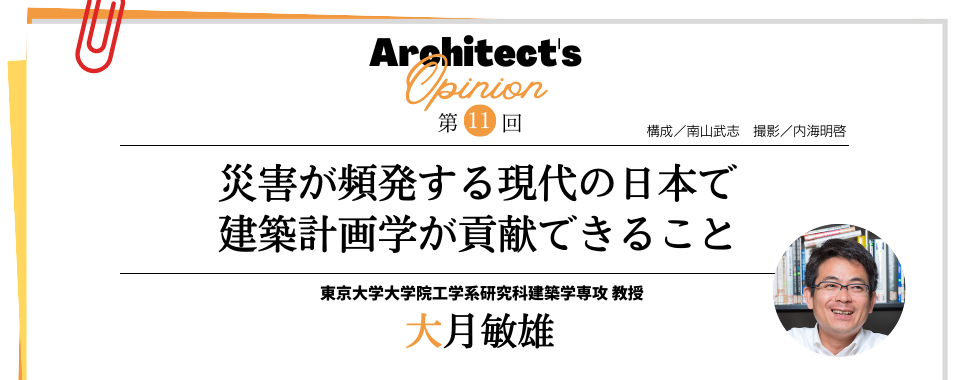これからの日本社会を考えれば、伝統の継承と新たな工夫が調和・融合する“創造的なまちづくり”は非常に重要なテーマである
三井所清典
50年を超える道のりにおいて、三井所清典は常に研究開発と実践を両軸に活動してきた。それは、設計だけにとどまらない「建築家が持つ多様な職能」を体現するものだ。大学院時代から携わった住宅の工業化、商業施設のシステムズ・ビルディングの開発では時代に先駆けた事績を残し、個々の建物に対しても、建築の目的と同時に手段について広く考察する姿勢を貫いてきた。また、1980年に竣工した「佐賀県立九州陶磁文化館」の仕事を機に始めたまちづくり活動は、三井所のライフワークとなっている。現在は日本建築士会連合会の会長として、地方独自の文化・風土を踏まえた建築設計と、それを担う「まちづくり建築士」の活動推進に心血を注ぐ。三井所が見据えているのは産業全体と、その未来である。
建築工業化から地域に根ざす建築・まちづくり活動へ
研究の意義をも見いだした三井所は大学院に進学し、そのまま内田研に在籍。卒論テーマで扱ったように、当時は日本の住水準が低く、住宅の供給も追いつかない時代であった。建築設計者として社会に何を提供できるか――住宅産業の台頭と歩を合わせ、三井所は集合住宅の工業化に関する研究開発に取り組み始める。
●
年間100万戸以上の住宅生産が求められていた時代です。個人住宅一軒の設計から工事完了までを考えると、1年に5戸つくるのが精一杯。当時の話として、仮に住宅設計者が2000人いたとしてもせいぜい1万戸、需要に対して全然寄与できない。ならば集合住宅の工業化を研究しようと。この時、内田先生から教示されたのがプレハブ集合住宅のモデル設計でした。その限りなく実務に近いプロジェクトを進めるために、院生たちで立ち上げたのが「GUP」というグループ。GUP1は調査研究だけでしたが、GUP4まで、博士課程が終わるまでに3つのプロジェクトをまとめました。構造の専門家などにも入ってもらって、「実際に建ててもいいようなもの」をね。ちなみに、H型鋼とPCを用いた高層集合住宅設計のGUP3は、後にNTTで評価してもらい、社宅として高層住宅が4棟実現したんですよ。
一方、〝実際につくる〞経験も得たかった私は、原さんが主催する「RAS設計同人」にも加わって、いろんなコンペに参加したり、実設計の手伝いをしたりしていました。なかでも記憶に強いのは、大規模小売店チェーンの店舗建設システムの開発です。「店をつくる合理的な生産方法を考えてくれ」という依頼を受け、我々が開発したのは、立地や規模の条件によって平面形が変わり、階数も3階から8階まですぐに対応できるフレキシブルな建築システム。従前のプレハブとは異なり、メーカーではなく発注者がシステムを所有するという点でも、新しい考え方となりました。
でも、問題が残った。新システムでは扱う材料も工法も違ってくるから、それまでチェーンの店舗建築にかかわっていた人たちの仕事を奪ってしまった。すごく困らせたという思いが残ったのです。少々過激な言い方をすれば、「革命を起こすと人が死ぬ」。以来、つくり方は革命ではなく修正にすべきだと考えるようになりました。一般の工業製品とは違って、建築は100年以上続くものでしょう。つくり手を生かしながら新しいものにつなげていく、その重要性に気づかされた仕事です。
●
博士課程修了後、芝浦工業大学の講師に就任した三井所は、追って「アルセッド建築研究所」を設立。当初の主たる活動は、引き続いての建築工業化に関する研究開発であったが、77年に始まった佐賀県有田町での仕事を契機に、その方向は大きく転換する。
●
「君は佐賀の出身だから一緒にやらないか」と、内田教授からの誘いを受けて携わったのが佐賀県立九州陶磁文化館です。最初はよくわからないままついて行ったんですけど、現地で町並みを見ながら調査を続けるうちに「これはすごいな」と。町内にはRC造の四角い建物が建ち始めていたものの、江戸時代から息づく総漆喰塗りの木造建築もちゃんと残っている。いかにも「伝統の焼き物のまち」といった風情で、その焼き物にしても陶工たちが十何代と継承してきたわけです。しかも決して古典的ではなく、ダイナミックな進化も感じられて感動的でしたね。
有田の地と調和し、町民が寄せる熱意に応えるには、「伝統を尊んだ現代建築」を実現せねばと強く思いました。でも最初は、スケッチをすれば四角くなるし、模型をつくってもピンとこない。有田では自然に映る傾斜屋根にも素直に取り組めませんでした。それまで教わってきたこと、やってきたこととは全然違うから。心がけたのは〝普通に〞調和するもので、部分的に新しい技術やアイデアを加えること。実際、陶磁文化館は一見普通に見えるけれど、例えばコンクリートの躯体は長寿命を目指して三層構造にするなど、画期的な技術を取り入れています。長持ちして性能のいいものは、伝統の流れのなかで抵抗なく受け入れてもらえる。いい建物ができたと思いますね。
この仕事で、私は大転換を迎えたのです。プレハブはやめよう。それまで一貫して普遍性のある建築をやってきましたが、「その地にふさわしいもの」をつくろうと。周囲からは「プレハブを裏切るの?」なんて言われましたが(笑)、一定の確立はできたと思っていたし、まだ手つかずだった分野、まちづくりで次の役割を果たしたいと考えるようになったのです。
- 【次のページ】
- 数々のプロジェクトを通じて職能の多様性を存分に発揮する

- 三井所清典
1939年2月7日 佐賀県神埼町(現神埼市)生まれ
1963年3月 東京大学工学部建築学科卒業
4月 RAS設計同人参加
1965年3月 東京大学大学院数物系研究科
建築学専攻修士課程修了
1968年3月 東京大学大学院工学系研究科
建築学専攻博士課程修了
4月 芝浦工業大学講師
1970年8月 アルセッド建築研究所設立
1973年4月 芝浦工業大学助教授
1982年4月 芝浦工業大学工学部建築学科教授(現名誉教授)
2007年4月 東京建築士会会長
2012年4月 日本建築士会連合会会長
家族構成=妻、息子2人
- 主な受賞
日本建築家協会優秀建築賞、
日本建築学会作品選奨、
日本建築家協会環境建築賞 最優秀賞、
BCS賞、
日本建築家協会新人賞、
新建築賞、
日本商環境設計家協会 JCDデザイン賞 大賞、
GOOD DESIGN AWARD 金賞、
ARCASIA Awards for Architecture 2016,
Building of the Year、
WAN Sustainable Buildings of the Year, Winner、
ar+d Awards, First Prize
ar+d Awards for Emerging Architectureほか多数