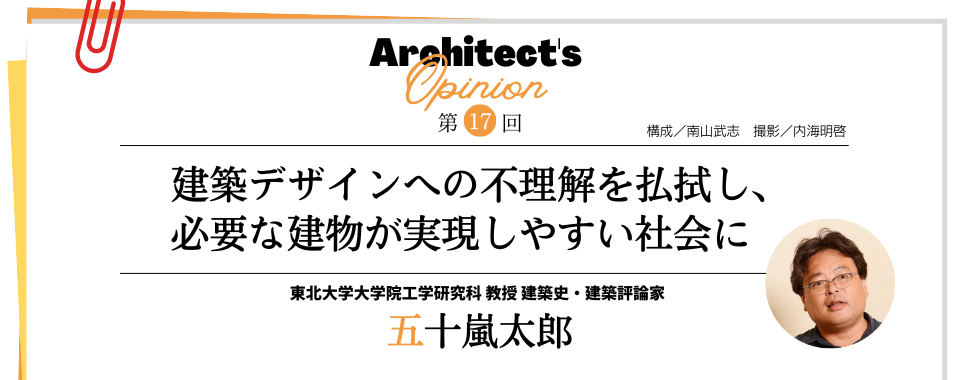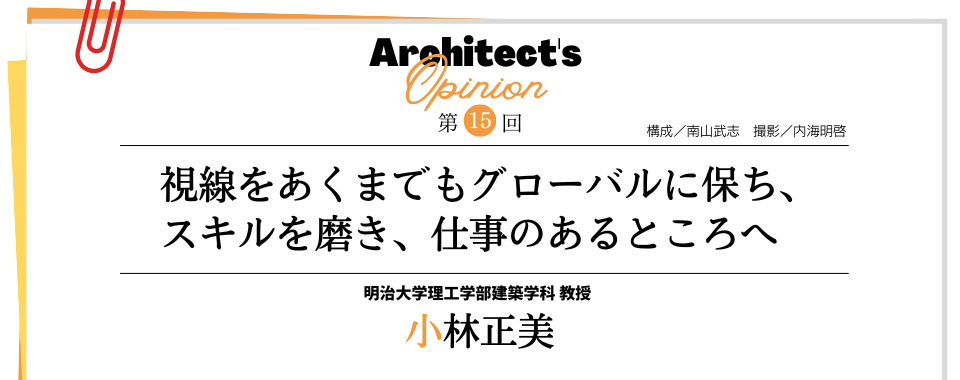主役はあくまでも建物が建つ場所や使う人で、建築家は脇役。主役との関係性のデザインを追究し、最適解を出すことが我々の職務である。
中村拓志
処女作「ランバン・ブティック銀座店」、「東急プラザ表参道原宿」「リボンチャペル」などの作品で知られ、数々の受賞歴を持つ中村拓志は、まさに若手建築家におけるトップランナーだ。手がけた作品はどれも強烈な印象を残すが、特徴的なのは、一つとして同じテイストを持たないことである。中村の根源をなすのは、地域の固有性や利用者にとことん寄り添う姿勢であり、だからこそ常に〝そこにしかないもの〞が生まれる。「主役はあくまでも建物が建つ場所や使う人。建築家は脇役である」――こう明言するように、中村は作家性に基づいた建築を是としない。主役との関係性のデザインを追究し、最適解を導き出すことが建築家の職務であると考えている。
28歳で事務所を旗揚げ。意欲的な作品を世に問い続ける
3年間の修業を経て「NAP建築設計事務所」を立ち上げたのは2002年、28歳の時だった。ほどなくして中村は、「ランバン・ブティック銀座店」でその確かなスキルとセンスを発揮するのだが、「仕事も実績もなし」で始めた当初は、当然ながら苦労もあった。
●
最初は自宅でホームページをつくっていたんですけど、もうつらくて。電話一本かかってこない日が続くと、絶望的な気持ちになりますよ。これはまずいと思って、友人に「一緒に事務所をつくろうよ」と声をかけ、今でいうシェアオフィスを借りました。隙間風ピューピューの小さな部屋ですけどね。隈さんの事務所時代に縁のあった業者さんが、見かねてオフィスビルの仕事を回してくれたこともあったのですが、途中で立ち消えになり、貯蓄も底を尽いて、もう終わりかと……。
でも頑張っていれば、必ず応援してくれる人やチャンスに巡り合えるものです。僕にとってはランバンがそう。先のプラスチックハウスが、たまたま来日していたランバンのデザイナーの目に留まり、それが縁で声がかかったのです。もうすぐ解散かという状況だった僕には夢のような話で、早々にパリに呼ばれた時は背伸びして、カッコつけて行ったのを覚えています(笑)。
アイデアを出したのは早く、イメージどおりの作品に仕上がりました。家族のために服をつくるところから誕生したブランドなので、銀座の中央通りに可愛い家がポコッと建った感じにしたかった。そして、宝石を縫い付けたランバンのドレスに着想を得たのが外装。約3000個のアクリル円柱を、温度差による収縮を利用した「冷やし嵌め」にしました。このたくさんのアクリル窓が極小のショーウインドウになり、かつ光を取り込むことで美しい現象をつくり出すのです。何の実績もない僕に自由な提案をさせてくれて、ランバンと一緒に議論しながら膨らませていったこの仕事は、プレッシャーを大きく超える楽しさがありましたね。
●
高い評価を得たこの処女作が実績となり、以降、中村は次々と作品を手がけていく。本人にとっても印象深い初期作品としては、小さな住宅「House SH」や都心の集合住宅「Dancing trees, Singing birds」、美容院「Lotus Beauty Salon」などが挙げられる。いずれも中村が主題としてきた「自然や身体との呼応」が貫かれており、その固有性から表情も実に様々だ。
●
なかでも、思い出深いのはHouse SHです。住宅密集地に建つこの家の最大の問題は、室内に直射日光を導けないことでした。考えたのは、外壁にぽっこりした膨らみを持たせて柔らかな曲線壁をつくり、そこに生まれた奥行きにトップライトから光を届けるという設計。そして、その膨らみは室内ではベンチになっていて、壁に座ったり、寝そべったりできる。文字どおり建築と身体が近い建築で、これができたのは大きかった。
作風の転機になったのはDancing trees, Singing birdsですね。敷地に残る木々を極力伐採しないで容積を最大限確保し、全6戸の部屋すべて、森と共に生活できるような配置にしました。都心でありながら環境保護と経済原理を両立させ、自分の信念を社会に問うようなものづくりができたと思っています。同時に、改めて知ったこともある。ランバンでは外壁に開けた穴から人工的に光を取り込み、美しい現象をつくり出したわけですが、やっぱり自然の木漏れ日の美しさにはかなわない。木に寄り添う建築を志向するようになったのは、このプロジェクトからです。
ただ、木々を残すための設計工程は大変でした。樹木医と一緒に根の位置を調査し、どうしても根に当たってしまう地中梁は蛇行して避ける。あるいは、張り出す枝は三次元測量し、強風時の揺れなどをシミュレーションして、枝の及ばない空隙を割り出す。今は三次元測量の技術も上がっていますが、当時は前例もなく手探り状態でした。それまでは木をドーンと伐採し、更地にしてから設計するのが〝当たり前〞でしたからね。結果、仮に容積が減ったとしても、住宅の付加価値が上がる方法論を示したことは、多少なりとも社会に影響を与えたように思います。
- 【次のページ】
- 公共建築に進出。培った経験やスキルを、豊かな未来へと紡ぐ

- 中村拓志
1974年2月12日 東京都生まれ
1999年3月 明治大学大学院 理工学研究科博士前期課程修了
4月 隈研吾建築都市設計事務所入所
2002年11月 NAP建築設計事務所創業(2003年7月に法人化)
- 主な受賞
日本建築家協会優秀建築賞、
日本建築学会作品選奨、
日本建築家協会環境建築賞 最優秀賞、
BCS賞、
日本建築家協会新人賞、
新建築賞、
日本商環境設計家協会 JCDデザイン賞 大賞、
GOOD DESIGN AWARD 金賞、
ARCASIA Awards for Architecture 2016,
Building of the Year、
WAN Sustainable Buildings of the Year, Winner、
ar+d Awards, First Prize
ar+d Awards for Emerging Architectureほか多数