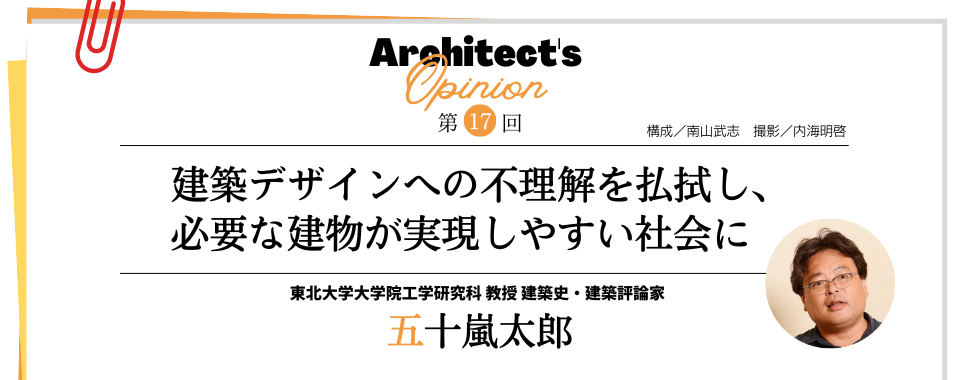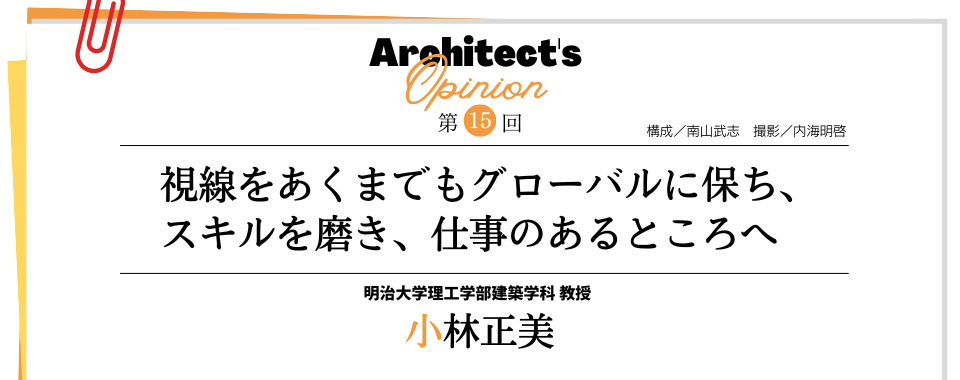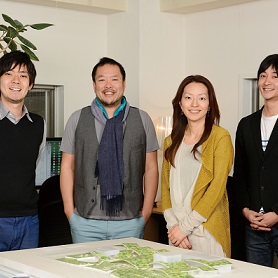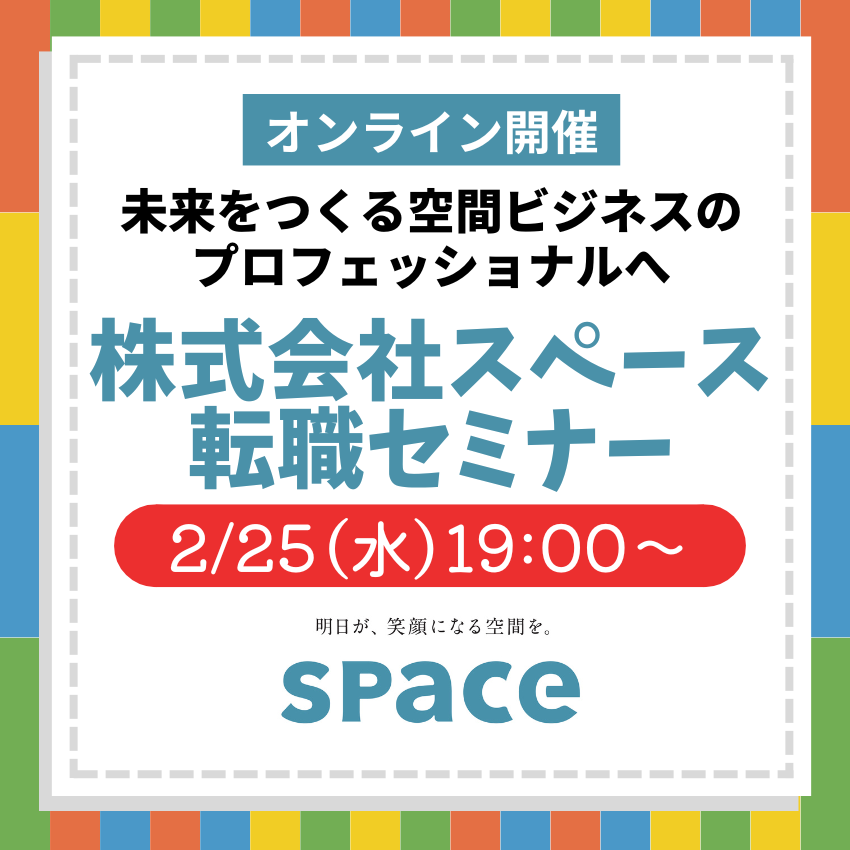主役はあくまでも建物が建つ場所や使う人で、建築家は脇役。主役との関係性のデザインを追究し、最適解を出すことが我々の職務である。
中村拓志
処女作「ランバン・ブティック銀座店」、「東急プラザ表参道原宿」「リボンチャペル」などの作品で知られ、数々の受賞歴を持つ中村拓志は、まさに若手建築家におけるトップランナーだ。手がけた作品はどれも強烈な印象を残すが、特徴的なのは、一つとして同じテイストを持たないことである。中村の根源をなすのは、地域の固有性や利用者にとことん寄り添う姿勢であり、だからこそ常に〝そこにしかないもの〞が生まれる。「主役はあくまでも建物が建つ場所や使う人。建築家は脇役である」――こう明言するように、中村は作家性に基づいた建築を是としない。主役との関係性のデザインを追究し、最適解を導き出すことが建築家の職務であると考えている。
学生時代に確立した建築の理想像に向けて、実践に踏み出す
大学院に進んだ中村は、引き続き阪田氏に師事しつつ、途中の1年間は早稲田大学の古谷誠章氏やAラボの吉松秀樹氏の下でも学んだ。「他流試合のつもりで」という表現は、常に自ら動いてきた中村らしい。こうした流れのなかで自分の志向を確認し、「どういう建築家になるか」、その像を明らかにしていったのである。
●
古谷先生の研究室には当時のアイデアコンペで名を挙げる人が多かったんです。僕自身、ステップアップしたい気持ちが強かったし、どんなすごい人たちがいるのか近くで感じてみたかった。一人で行くには勇気がいりましたけれど。古谷研に研究生として籍を置かせてもらった1年間は、行ったり来たりの生活でしたが、〝外〞を見られたのは本当にいい経験になった。生意気な学生ながら、可愛がってくれる先生方に恵まれたことはやはり感謝ですね。
地域経済学をやっていた親父からも影響は受けたのでしょう、地域主義というか、地域の固有性を大事にしながら設計に臨むスタンスは早くから定まっていました。加えて、学生の頃から「自然」や「身体」というものに対して問題意識が強かったから、これらと建築が濃密な関係性を持つものをつくりたいと、ずっと考え続けてきました。
その身体性をテーマにしたのが、大学の卒業設計「ホーキングの家」。車椅子の宇宙物理学者・ホーキング博士の住宅で、観点としては「身体を拡張する」です。テクノロジーの力を借りて、自由に動きながら用を足していくような家。例えば眼鏡や杖、車椅子もそうですが、人間の身体性は「その時代の技術によって拡張されていく」という考えに基づいて設計したものです。これは、最初から最優秀賞を狙って戦略的に取り組み、実際に取れたのですが、よりうれしかったのは阪田先生からの「人は論理じゃなく、言葉にならない部分で感動するものだ」という批評コメントです。建築はコンセプトや論理でつくり、説明するものと頑なに信じていた僕の目を開かせてくれた。言葉にならない部分に建築の豊かさがある――今も、その思いは変わっていません。
●
「アトリエで3年間修業する」と決めていた中村が選んだ先は、隈研吾建築都市設計事務所。バブル崩壊の後遺症が色濃かった1990年代後半は、隈氏が路線の大転換を図り、仕事の舞台を地方に移した時代である。地域や自然環境としっかり向き合うその姿勢は、まさしく中村の志向と合致するもので、「とてもいいタイミングだった」。
●
様々なコンペで審査員を務めていた隈さんとは、学生時代から面識がありました。いつも会場にいる僕に「またお前か」と(笑)。そのうち「事務所に来ないか」と誘ってくださるようになって。折しも、隈さんの代表作となった「那珂川町馬頭広重美術館」の模型を見る機会があり、地場産の杉材を使ったルーバーであるとか、人の知覚に影響を与えるような建築に感動したんですね。自分が大事にしているテーマと同じ。「隈さんに学びたい」と強く思ったのです。まだ10人くらいの事務所規模で、それもまた魅力的でした。
とはいえ、新人がすぐに実務に就けるわけもなく、最初は焦っていました。「コンペが上手い」ということで、いきなりコンペチームのリーダーとなり、1年くらいは提案業務ばかり。焦りは募ったけれど、ただ、隈さんやクライアントの近くにいられて、そこで交わされる会話やプレゼンテーションを見られたのはすごくいい経験で、今に生きる学びとなったのは確かです。
僕は、小規模な建築を繰り返し経験することが独立への力になると考えていたので、小さくて面白そうな案件が出てくれば「やります! やります!」と(笑)。手を挙げてかかわったものには、山形県銀山温泉の浴場や、個人邸宅のプラスチックハウス、熱海の旧蓬莱旅館の古々比の瀧(こごいのゆ)などがあります。住宅のほうは、FRPを使って温かな空間をつくり出すことに挑戦したもので、まさに素材との格闘。FRPの型のパーツを机にバーッと並べて、手で触りながら、あるいは職人さんと対話しながらつくっていく工程はものすごく勉強になった。そして温泉はね……何といっても完成後の一番風呂が最高(笑)。体で建築の素晴らしさを感じた大きな経験です。実務を通じて、一層、肌感覚や快適さを大事にしたいと考えるようになりました。逆に言えば、いくら論理的に語れたところで、それがなければ建築には何の魅力もないとわかったのです。
- 【次のページ】
- 28歳で事務所を旗揚げ。意欲的な作品を世に問い続ける

- 中村拓志
1974年2月12日 東京都生まれ
1999年3月 明治大学大学院 理工学研究科博士前期課程修了
4月 隈研吾建築都市設計事務所入所
2002年11月 NAP建築設計事務所創業(2003年7月に法人化)
- 主な受賞
日本建築家協会優秀建築賞、
日本建築学会作品選奨、
日本建築家協会環境建築賞 最優秀賞、
BCS賞、
日本建築家協会新人賞、
新建築賞、
日本商環境設計家協会 JCDデザイン賞 大賞、
GOOD DESIGN AWARD 金賞、
ARCASIA Awards for Architecture 2016,
Building of the Year、
WAN Sustainable Buildings of the Year, Winner、
ar+d Awards, First Prize
ar+d Awards for Emerging Architectureほか多数