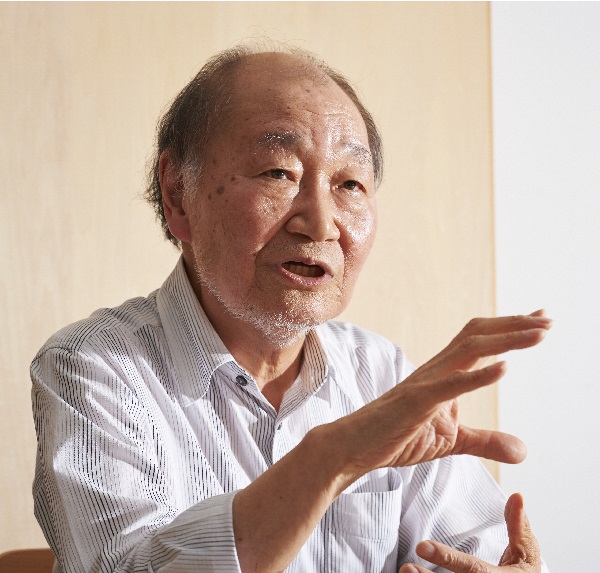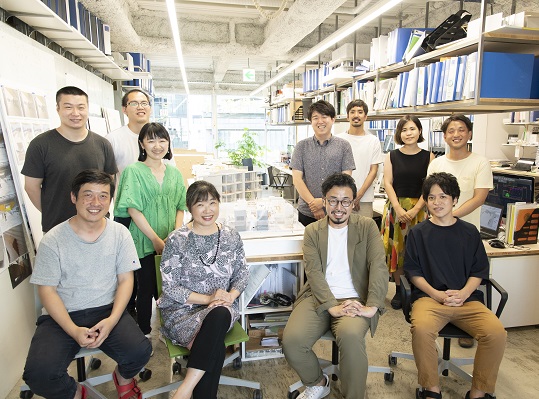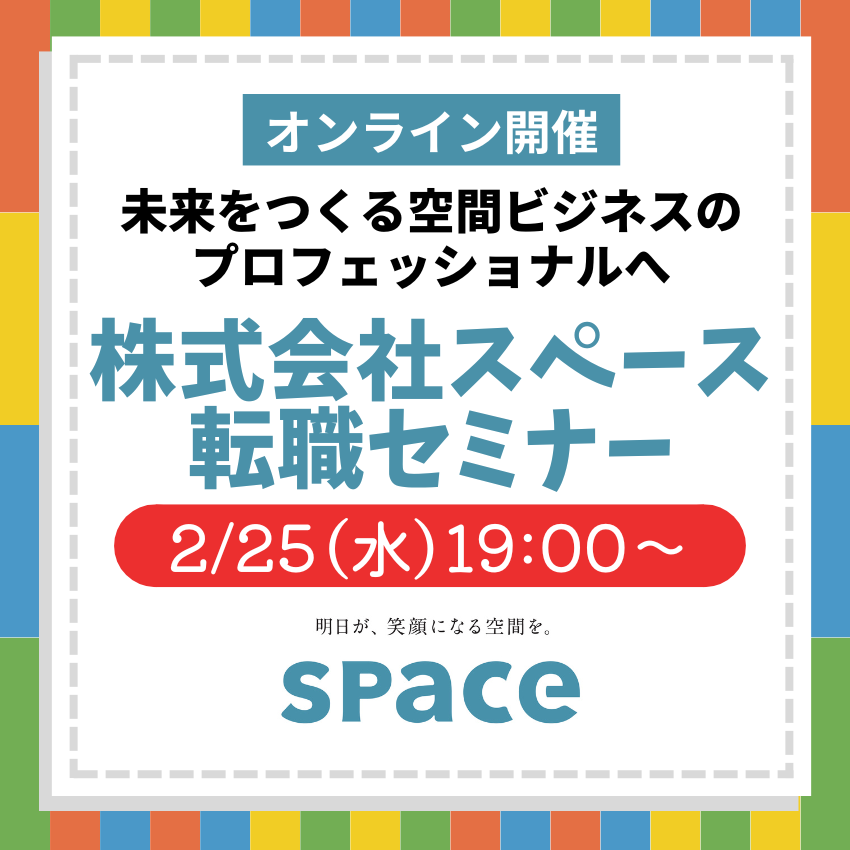21世紀の建築はどうあるべきか。地球全体に、どう寄与していくか。僕らの世代は、その道筋をつけていく責務があると思う
仙田 満
26歳で独立した時、仙田満(せんだ・みつる)は自分の名を冠した事務所ではなく、「環境デザイン研究所」という屋号で旗揚げをした。建築だけでなく都市、造園、インテリア、展示、遊具、プロダクトデザインなど、広い領域で設計に携わっていく――そう決めていたからだ。以来50年近く、仙田は“環境デザイナー”として、才を発揮した数多の作品を発表、その世界を切り開いてきた。なかでも、成育環境のデザインという分野では第一人者である。子どもが元気に育つ環境づくりをライフワークとしながら、日本建築学会や日本建築家協会の会長職も務め、業界を俯瞰した社会活動にも尽力。「今の社会システムを変えなければ、日本の環境デザインは育たない」。穏やかな風情ながらも、仙田の胸には次代への熱き思いが溢れている。
「文理の中間領域」を求めて。大学生の時、建築に目を向ける
仙田が生まれ育った横浜市保土ケ谷区には斜面緑地が多く、当時、あちこちに掘られていた防空壕が、子どもたちの格好のあそび場だった。「今の子どもに比べると、日々のすべてがあそびにつながっていた時代」。わんぱくだった兄について回る一方で、仙田がとりわけ夢中になったのは、絵を描いたり、工作することだった。
●
少年雑誌に付録としてついていた工作とか理科の実験キットにワクワクし、片っ端からつくっていました。絵もね、小学校の先生に「これ何?」と言われるような具合だったけれど(笑)、描くのが楽しくて。手作業が好きなのは、造船所で工員をしていた親父の影響かもしれません。近くの弘明寺というまちに横浜国大の工学部があったのですが、親父自身興味があったようで、そこの大学祭に毎年連れていってくれたのです。今のようなお祭り感覚ではなく、大学でやっている様々な研究を市民に公開する場で、白衣を着た大学生たちがカッコよかったし、僕も科学技術に興味を持つようになっていました。
中学生の頃は基本的に理系だったし、僕は工業高校に進んで、卒業したら働くつもりだったのです。そもそも周囲には、大卒の人なんていないような地域ですよ。ところがある時、中学の担任が、お袋に「仙田君を工業高校に行かせるのはもったいない」と言ったそうで。それで話が変わり、僕は、湘南高校に進むことになったのです。
中学校ではそれなりによかった成績が、進学校ですからね、入ってみれば500人中350番くらいの成績。それにショックを受けて猛烈に勉強し、シングルまで順位を上げていったというガリ勉の3年間でした。ただ、この頃は映画や文学にも惹かれ、試験が終わるたび映画館に足を運んでいました。できることなら映画監督になりたい……そんな夢を抱いていた頃です。
●
遡れば、この時分から仙田には“境目”というものがない。文系も理系もなく、興味を持った分野を広く学んでいた仙田は、進学先として東京工業大学を選ぶ。当時、同大学が先んじて設置していた経営工学コースに「文理の中間領域」と「新しさ」を感じたからである。そして、ここで初めて、仙田は建築に目を向けるようになる。
●
入学した年の全学祭の時、たまたま建築科の先輩学生に「研究発表を手伝ってくれ」と声をかけられたのです。聞けば、人間疎外と科学技術というようなテーマで、面白そうだった。これ、すごかったんですよ。自分の考えを映像や音楽を用いてスライドにまとめ、表現する。今でいうマルチ・プレゼンテーションで、ほかの発表手法とは全然違ったのです。当時はまだ大きな模造紙に手描きという形式が主流でした。こんなかたちがあるのかとインパクトを受けたし、建築を学ぶ先輩の影響で、僕は、求めていた文理の中間領域に「建築」があることに気づいたのです。
それで建築科に進み、谷口吉郎研究室に入りました。谷口先生は、島崎藤村の出生地である岐阜県の馬籠に「藤村記念堂」をつくった人で、文学者との交流も持つ異色の建築家。そして、いち早く「環境の意匠」という言葉を使い、日本の環境というものを概念化した。大きな影響を受けましたね。
学生時代の研究テーマは「歴史的空間論」。特に、日本の城の研究です。城の様式というのは、1500年代後半に一定の完成をみるのですが、鉄砲50伝来からわずか50年ほどで、石垣とか木造高層建築とか、その様式が確立されているのです。なぜ、そんな短期間でできたのか。僕の結論としては、コラボレーション。かつての宮大工とは違った新しい技術人、すなわち下克上した田舎大工、渡来した南蛮人、そして例えば千利休のような新たな都市文化人、これら多様な能力を持つ人々のコラボレーションによって、「城」というシステムができたと考えたのです。「多様なデザイナーの協働が新しい時代の様式をつくる。」この結論は、僕の環境デザインの原点ともいうべきものです。
- 【次のページ】
- 「環境デザイナー」としての礎を築く。そして独立へ

- 仙田 満
Misturu Senda 1941年12月8日 横浜市保土ケ谷区生まれ 1964年3月 東京工業大学理工学部建築学科卒業 4月 菊竹清訓建築設計事務所入所 1968年4月 環境デザイン研究所を設立し、 代表に就任
2001年6月 日本建築学会会長(~2003年) 2004年4月 こども環境学会会長(~2010年) 2005年4月 東京工業大学名誉教授 10月 日本学術会議会員(~2011年) 2006年6月 日本建築家協会会長(~2008年) 2010年4月 公益社団法人こども環境学会代表理事
- 主な受賞歴
- 毎日デザイン賞(1978年)
- BCS賞(1987年、2011年)
- BCS賞(1987年、2011年)
- 日本造園学会賞(1996年)
- 日本建築学会賞(1997年)
- IOC/IAKS賞 (1997年、2001年、2005年、2009年、2011年)
- アルカシア建築賞ゴールドメダル(2010年)
- 日本建築家協会賞(2010年、2011年)
- 村野藤吾賞(2011年)
- 日本建築学会大賞(2013年)
ほか多数
- 講師・教授歴
- 日本大学芸術学部講師
- 早稲田大学理工学部講師
- 琉球大学工学部建設工学科教授
- 名古屋工業大学社会開発工学科教授
- 東京工業大学工学部建築学科・ 大学院理工学研究科建築学専攻教授
- 慶應義塾大学大学院特別研究教授
- 愛知産業大学大学院教授、放送大学教授
などを歴任